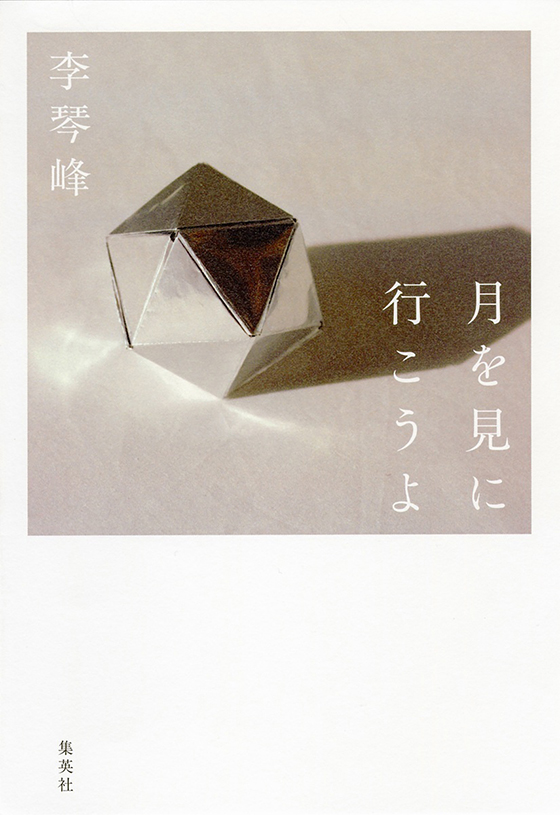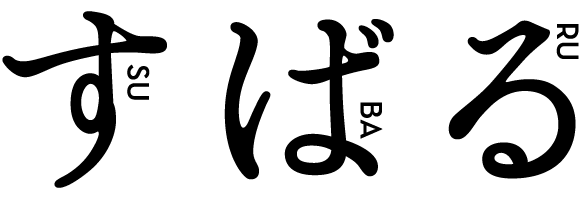【書評】美しい夜を共に生きるために
倉本さおり
〈私は山を動かすことはできないが、光を灯すことはできる〉――IWPの創設者のひとり、詩人のPaul Engleの墓石に刻まれている彼の詩の一節だそうだ。
光を灯す。それは、周縁に追いやられ、社会から見えなくされた人びとの姿を照らしだし、居場所をつくる行為でもある。まさにこの本の根底に流れる精神と響きあっているように思える。
世界各地から詩人や小説家などの文筆家が招かれ、十週間にわたって滞在・交流するアイオワ大学の国際創作プログラム・IWP(International Writing Program)。本書は、2023年に同プログラムに招かれた作家・李琴峰が、そこで見聞きし、肌で感じた物事から思索をひろげながら綴ったテクストだ。
見聞録、あるいは体験記、と端的に言い切ってしまえないのは、作者である李自身がこの本を「小説」と定義しているから。実際、李自身の創作をはじめ、本文にはプログラムの参加者たちの発見や思いつきから芽吹いた大小さまざまなフィクションが接ぎ木のように差し挿まれる。その色とりどりの想像の鮮やかさったら!
例えば「赤い大地と青い湖」という章。熱波に覆われたアイオワシティの酷暑のなか、飲み物に使われた大量の氷がそこらじゅうの芝生に捨てられているのを見て、香港の女性作家Evaは滞在中に執筆した小説のなかに「芝生から生えてくる氷」なるものを登場させる。李自身はといえば、異常気象に起因するとうもろこし畑(※アイオワ州はアメリカ最大のトウモロコシ生産地)の大火事によって「赤い大地の人々」が燃えあがり、ペンより重いものが持てない「青い湖の住人」たちを飲み込んでゆく「出まかせ」を語りはじめる。
また、「紙コップ戦争」という次章では、参加者たちの滞在するホテルが「景色のある部屋」と「景色のない部屋」に二分されてしまうこと、そして不運にも「景色のない部屋」をあてがわれた作家たちのしょんぼり感と奇妙な連帯感が活写される。あまりに殺風景な景観のなかで、投げ捨てられた紙コップにすら愛着を感じてしまったらしい詩人の四元康祐が、写真と共に思いつきの投稿をしたのを皮切りに、「景色のない部屋」の住民たちがさながら大喜利のように紙コップポエムないし紙コップ哲学をグループチャット上で披露していく流れには読みながらにやにやしてしまった。じつに作家らしい、ウィットに富んだやりとりだろう。「『景色のない部屋』に住むことが、一種のアイデンティティみたいな感じになってるね」――この出来事を、李はスラップスティックな闘争劇へと想像のなかで組み替えていく。最終的に「西側諸国と東側諸国の大規模な戦争へと発展」するその諍いが、性別や人種や個人の主義・思想とは無関係な、ただのホテルの部屋割りに端を発しているという点が、なんともユーモラスでありながらこの作家らしい鋭い批評眼を感じさせる。
〈――というくだらない幻覚を、私たちはもちろん見なかった〉
〈――後の世に「紙コップ戦争」と呼ばれるこの紛争は、もちろん起きなかった〉
ここで「もちろん」という語が繰り返されている点に着目したい。これらがあくまでフィクションであるということを敢えて強調する李の筆致は、けっして冷笑的なそれではなく、世の理不尽から懸命に距離をとろうとする切実さに縁どられているように思えるのだ。
IWPの参加者たちはみなそれぞれに複雑な陰影に満ちた背景を抱えている。例えば政治情勢を憂える詩をたくさん作っている香港出身のTammyこと何麗明は、「諸事情により」現在はパリに住んでいる。台湾出身のKevinこと陳思宏は、オープンリー・ゲイであり、二十代のときに「台湾から逃げ」るべくベルリンに移住した。また、イエメン出身の詩人Sabaは、内戦中のイエメンから三人の子どもを連れて出奔。各国を転々とし、難民キャンプも経験した彼女は、最終的にオランダに落ち着き、オランダ語で書いた詩で文学賞の候補となった。
そもそもIWP自体が「ディアスポラの中から始まったもの」なのだ。もうひとりの創設者・聶華苓は1925年に中国の武漢に生まれ、抗日戦争、国共内戦と続く戦乱のなかを逃げ回り、台湾へ渡ったあとも独裁政権と白色テロに苦しんだ。そんな彼女がPaulと出会い、アメリカ中西部の小さな大学街で始めたプログラム――それはまさに灯火だ。李自身をふくめ、「漂泊と越境」を繰り返してきた作家たちは、プログレス・プライド・フラッグがあちこちではためくアイオワシティでつかのま「解放されている感じ」を味わい、いくつかの「美しい夜」を共に過ごす。
だが、現実はそうやすやすと振り切れない。参加者のなかにはウクライナ出身の詩人もイスラエル出身の詩人もいる。李がアイオワに滞在した十週間のあいだにもロシア軍の侵攻は続き、ハマスによるテロが起きる。やがてイスラエルによる一方的なパレスチナ爆撃が始まると、参加者のあいだにあった緊張感ははっきりとした軋轢へと変わっていく。
本書の後半、プログラムの一環としてシカゴに渡った李が「道端で見ず知らずの人にいきなり顔を殴りつけられる」場面には思わず絶句してしまった。コロナ禍以降のアジア人ヘイトのありようを如実に物語るエピソードだが、それは2017年のトランプ政権誕生以来、箍の外れた差別感情が現実を侵食してきた一端でもあるのだ。
現実から非現実へ。日常から非日常へ。小説を「行きて帰りし物語」だと定義する李は、どんな現実の不合理に直面しても――それこそ拳で殴りつけられたときでさえも――けっして言葉を手放さない。なぜなら、言葉こそが彼女にとっての灯火であり、社会の闇のなかで自分自身を照らす唯一の手段だからだ。
「月を見に行こうよ」。それは非日常的なプログラムのなかでもたらされた「美しい夜」を象徴する台詞であると同時に、この小説の出口で待ち受けるわたしたちの現実へ向けて放たれた祈りでもあるのだろう。
どうかあなたとわたしが、お互いを奪わず、お互いを照らしだせる存在でありますように――と。