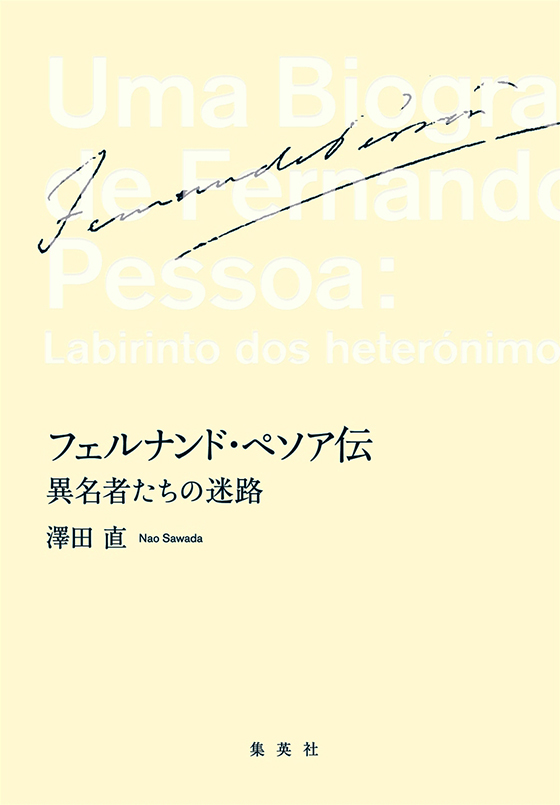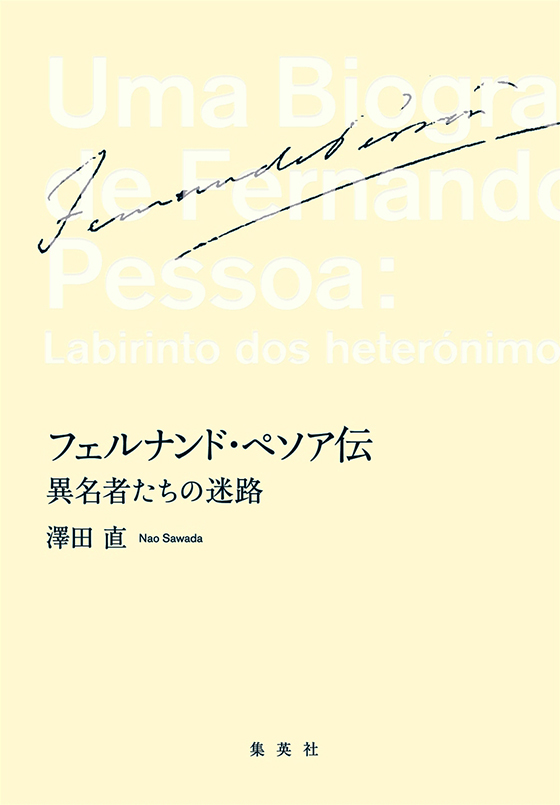【書評】「取り憑かれる」ということ
宮下志朗
詩人フェルナンド・ペソア(1888−1935)の大部な評伝。生まれはリスボンだが南アフリカで教育を受けて英語は堪能、成績トップなのに英国の奨学生となれず、リスボン大学は中退。いくつか起業するも頓挫して商業翻訳で生計を立て、生涯独身。この間、ペソア名義以外に「異名者」と呼ばれる経歴・性格・文体も異なる作者を多数創造して――素朴・異教的なカエイロ、古典的なレイス、前衛・未来派のカンポスの三名が代表的――、詩作を展開し、若き世代に支持される。刊行した詩集は、英語詩集を除くと、死ぬ前年の一冊だけ。だが死後、膨大な草稿がつまったトランクが発見されて、詩人の名声は一挙に高まり、いまやポルトガルの国民的詩人だ。
エピソード満載だが、やはり中心はペソアの代名詞たる「異名者」に関して。最初の「異名者」の出現は六歳のとき、「騎士パス」に扮して自分宛に手紙を書いた。なりすましの性向が一生続くのだ。前述の三大「異名者」については、その特徴が一覧表になっていておもしろい。カエイロは色白で金髪、牡羊座の金利生活者、レイスは眼鏡をかけた乙女座の医師、前衛カンポスは天秤座の造船技師だが、スコットランド留学経験ありという。長篇小説の主役なみにキャラをしっかり創造してある。ペソア本人は双子座だが、占星術師を志したこともあって、魔術・オカルトに惹かれがちだ。本人によると、「異名による作品は作者の人格の外」に存在し、三大「異名者」詩人の相互作用が「幕間劇の虚構」というドラマを構成するという。多重人格ではないのかとも思うけれど、そこは、かなり緻密に計算されたドラマトゥルギーであるらしい。著者も、「異名者」使用は「離人症」と紙一重だが、「存在論的で詩学的な事象」だとして、「模倣」や「擬態」をキーワードに説得力ある考察をしている。主要作品の紹介も懇切丁寧である。
それにしても、「異名者」は現実にも介入する困り者。詩人は三十二歳にして初恋を知り、積極行動して唇を奪った。ところが「異名者」カンポスがペソアを非難する手紙を彼女に送り、邪魔をした。破局である(その後、再燃はする)。この人の人生、どうやら頓挫が常数かと思われる。季刊文芸誌『オルフェウ』(一九一五)も、これを理念的・経済的に支えていた親友サ=カルネイロのパリでの自死によりあえなく二号で終刊、ペソアの抑鬱は深まった。
「異名者」のアイデアは、ヴァレリー・ラルボーの『A・O・バルナブース全集』(一九一三)に由来する説もとあって、思った。親友サ=カルネイロは留学先のパリで、ラルボーとの接点はなかったのか? ラルボーが常連だったアドリエンヌ・モニエの貸本屋兼書店《本の友の家》(一九一五年開店)はヨーロッパ最先端の文学を揃え、パリに集う各国の文学者たちのたまり場となっていくのだ。もしも雑誌『オルフェウ』がウィンドウに並んでいたら、ヨーロッパ文学史はどうなっただろう?
実業に惹かれていた詩人は宣伝コピーも書いている。「アメリカ流のリフレッシュ コカ・コーラ最初はギクッとする、次にグッと取り憑かれる」がそれで、飲み物の売れ行きも上々。だが「取り憑かれる」という表現が検閲に引っかかり――なにせ軍事独裁政権下だ――、依存性の麻薬ではとの口実で輸入禁止、なんとコカ・コーラは半世紀近くポルトガルには入らなかった。噓みたいな実話で、二〇一八年に映画にもなったらしい。でも、コーラはともかく、ペソアという詩人は「取り憑かれる」存在だ。イタリアの小説家アントニオ・タブッキ(1943−2012)がその代表。一九六〇年代、タブッキは留学先のパリでカンポスの詩集『煙草屋』の仏訳を読んでペソアに「取り憑かれ」、ポルトガルに留学した。訳者でもある須賀敦子との対談で語っている(「魂の国境を越えて」『須賀敦子全集 別巻』河出文庫)。小説家はついに、リスボンを舞台にして、ペソアのもう一人の「異名者」ソアレスの『不穏の書』を狂言回しに、ポルトガル語で『レクイエム』を書いてしまう(一九九一年、リスボン刊)。ポルトガル話者という「異名者」に「擬態」して、ペソアを鎮魂したのだろう。タブッキに遅れること二十数年、著者澤田直も同様の軌跡をたどる。「異名者」レイスの「ぼくらのなかには 無数のものが生きている(中略)自分とは 感覚や思念の劇場にすぎない(中略)たくさんの自分がいる けれども(中略)彼らを黙らせ ぼくが語る」といった詩を仏訳で読んで「取り憑かれ」、自分はペソアの異名者の一人かとまで妄想をたくましくした。ポルトガル語を学び、ペソアの詩や『不穏の書』を訳し――翻訳は「擬態」の一つ――、評伝に至った。敬服すると共に、そこまで読み手に「取り憑いて」離れない詩人の魔力に驚いた。
というのも、ペソアは短篇集『アナーキストの銀行家』しか読んだことがない(「独創的な晩餐」がお薦め)ぼくにも、ポルトガル文学に強く魅せられた時期があるのだ。本書で「写実主義を確立した」と形容される前世代の文豪エッサ・デ・ケイロース(1845−1900)だ。短篇集や『アマーロ神父の犯罪』を仏訳で読んで夢中になり、辞書や文法書を買い「o,os/a,as」(これは定冠詞の変化)とポルトガル語を学び始めた。そして本誌《すばる》に、「マンダランを殺せ――バルザックからエッサ・デ・ケイロスへ」という文章を発表もしたのだ(一九九四年六月号)。マンダラン(中国の大官)はケイロースの短篇『マンダリンO Mandarim』のこと、まだ邦訳はなく、出版社に働きかけて本短篇を収めた『縛り首の丘』(彌永史郎訳、白水社)を出してもらう。全集も購入した。でも、そこでストップ。仏訳で小説類を読んだ時点で、熱病はさめていた。要するに「取り憑かれて」はいなかったのだ。でも奇貨おくべし、ケイロースを再読してから、ペソアの詩にも挑戦したい。