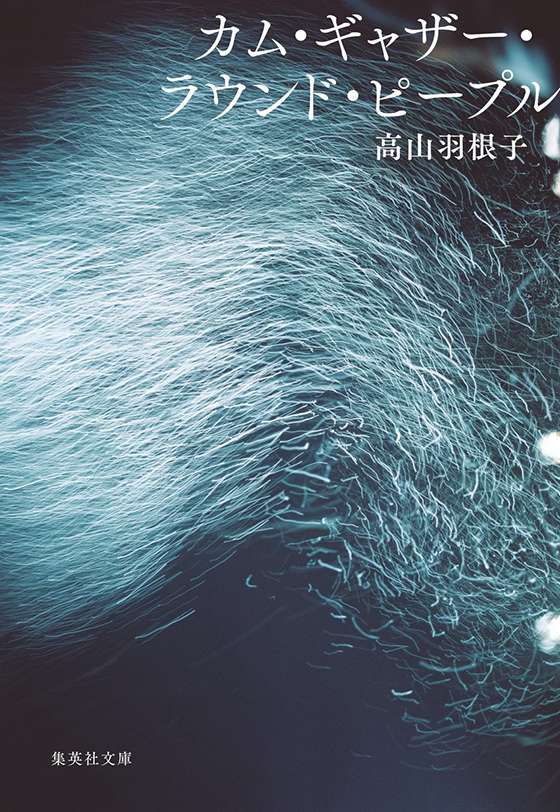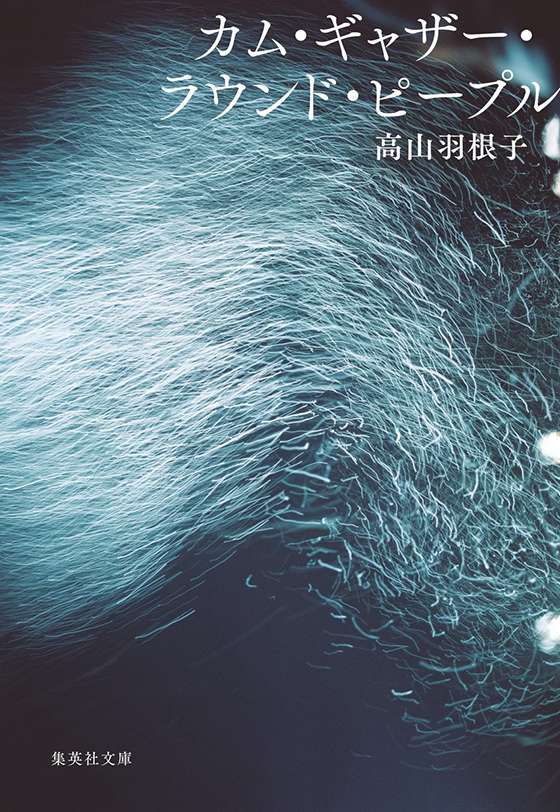内容紹介
おばあちゃんは背中が一番美しかったこと、下校中知らないおじさんにお腹をなめられたこと、自分の言い分を看板に書いたりする「やりかた」があると知ったこと、高校時代、話のつまらない「ニシダ」という友だちがいたこと……。大人になった「私」は雨宿りのために立ち寄ったお店で「イズミ」と出会う。イズミは東京の記録を撮りため、SNSにアップしている。映像の中、デモの先頭に立っているのは、ドレス姿の美しい男性、成長したニシダだった。
イズミにつれられてやってきたデモの群衆の中、ニシダはステージの上から私を見つけ、私は逃げ出した。敷き詰められた過去の記憶とともに、私は渋谷の街を思い切り走る。ニシダにつかまらないように。
【書評】ウォーターズ・アラウンド・ユー・ハブ・グロウン
酉島伝法
たいていの物語は、地図でいえばルートがある程度はっきり引かれていて、それを目安に進んでいくことができる。けれども、高山羽根子の作品ではおおむね何も示されていないし、こちらでルートを記しながら進もうにも道の繫がりが妙だったり東西南北が回転していったり、時には地図じたいがシャッフルされることもあり、いまどこにいるのかどこに向かっているのかが判らないまま歩むことになる。
本書もまた、ヘルメットについての思索で始まる冒頭から、いつにも増して読み手の足場がぼやけている。語り手は、歩道のでっぱりから車道にトン、と落ちるくらいのさりげなさで、思索から子供の頃のおばあちゃんとの記憶に滑り込む。それは想起というより、現在が不確定のまま子供の頃の自分と半ばまで融け合い、その幼い目から世界を眺めているような不思議な主観だ。
話が脈絡の見えないままずれていくのは、誰もが唐突になにかの考えを巡らせては未練なく別のことに気を取られるあの感じに似ている。読み手は移り変わる情景の中で先行きの判らないまま、これまで見過ごしていたものがくっきりと精細に立ち現れる様や、風変わりなエピソードの断片を追うのをやめられなくなる。まるで羽虫が見えていなかったおばあちゃんのように、普段自分は何を見ていたのだろうと不安にさせられるような鮮やかさだ。単に描写の解像度が高いというだけでなく(解像度が上がったために心霊写真が失われたことにも触れられている)、この本を開いている間だけ、知覚器官をなにか別のものにすげ替えられているかのような。
とりわけ鮮烈なのは、おばあちゃんの背中だ。これほど魅力的にひとの背中を描いた文章を他に知らない。お経を読むときの声の抑揚も。それら誰にも気づかれていなかったエロティシズムや、おばあちゃんの見たがった、けれどもその視力では決して見えなかったであろう雪虫の話を巡らせる間にも、語り手の頭にはヘルメットが固く残り続けていたことに、工事現場の男の話がはじまったところで気づかされる。読んだことを忘れたくなる気味の悪い行為を男にされるあいだ、語り手はじっと動けず、それを誰にも言えない。後にこの事件には他にも被害者がけっこういたのだと判るが、された女の子はかわいい子ばかりで、されなかった子をされた子がなぐさめるという見覚えのある地獄も広がる。こういった幾つもの事柄から、いまに至るまで続く女性が受容を強いられてきた理不尽さを相似的に浮き上がらせていく。例えば〝充電器とか、ばんそうこうとか、そういうものが追加されているだけなのに、なんで結果的にこんなに重くなってるんだろう? って〟という何気ない一文にも。
中学生の頃には、犬の紐をほどいてやろうと忍び込んだ学生寮で、男がギターでボブ・ディランの「時代は変わる」(The Times They Are a-Changin’)を弾いている。ここでは歌われないこの曲の一節が、本書のタイトルだ(そういえばアラン・ムーアの傑作コミック『ウォッチメン』の映画版のオープニング・タイトルでは、この曲をバックに、第二次世界大戦で活躍したヒーローたちが戦後は時代に取り残され、殺されたり強制入院されたりする様が描かれていて印象的だった)。
他にもあっぱっぱにラッタッタといった、かつてはさして気にもとめず、すっかり忘れてもいた言葉が、当時の空気をまといながら次々とよぎってはっとさせられる。誰もが目にしたことのある、ベトナム戦争時に、ナパーム弾の空襲から泣きながら逃げてくる素っ裸で両手を広げた少女の写真も現れる。語り手は、この写真では見えない彼女の背中に思いを馳せる――よく知られていることだが、少女は当時九歳で名前をファン・ティー・キムフックといい、このとき全身に火傷を負ったものの撮影したカメラマンや記者に助けられ、十七回もの手術を経て一命を取り留めた。後にカナダに移住し、反戦運動家となる。キムフックの火傷の痕に覆われた背中は、息子を抱いたものなど、幾つもの写真で目にすることができる。まったく異なる描写だというのに、語り手のおばあちゃんの背中を連想せずにはいられない。
こうした読み手を巻き込む想起や思索の乱反射を経て、いま現在の出来事が語られはじめるのは、ようやく43頁になってからだ。とはいえ小説における現在という約束事をほぐすような文体は変わらない。そしていま電車の運行が止まり、語り手が雨を逃れて風変わりな店を訪れてから、小説の地図にルートらしきものが引かれはじめる。その店で知り合ったイズミという女性に、彼女の撮影したデモに集まる人々の映像を見せられた語り手は、これまで遠巻きにしていた過去のひとつ――それは具象化されたいまの社会のようでもある――を目の当たりにする。
やがて脈絡のない、途切れた道ばかりに見えたこの小説の地図に幾つもの裂け目が生じ、複雑に折り畳まれて隠れていた背中のような領域が、つながりが垣間見えてくる。
語り手は過去に近付こうとしながらも、背を向けて衝動的に駆け出し、映像をうつす画面だらけの街から、自らの記憶から、収まりのよい結末を先読みしようとする読者から、まるでナパーム弾の爆撃を受けたベトナムの少女のように逃げていく。それは、心の中の声と実際の声とが重なり合うそのときまで続くだろう。
隠された背中まで覗き込んで、可能なかぎりあらゆる視点で物事を拾い上げようとする真摯さと――などと書きかけて立ち止まる。『カム・ギャザー・ラウンド・ピープル』は、こうして安易にまとめようとする力に抗う作品だ。