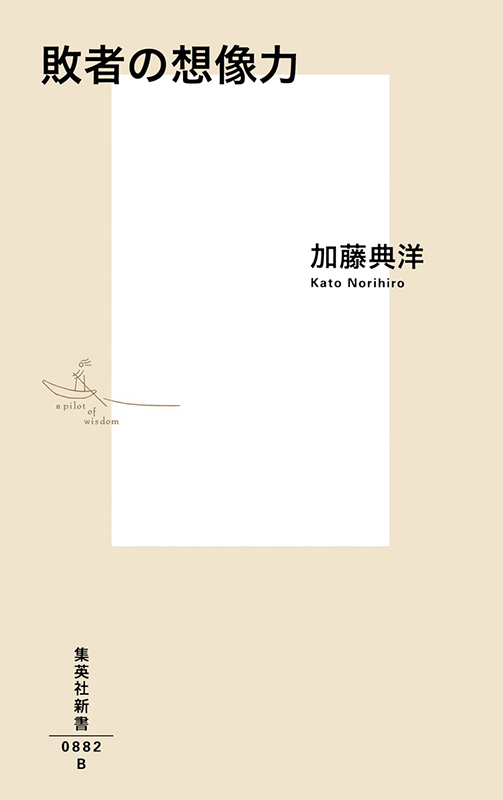【書評】戦後七〇年の間に生み出されたものをめぐって
沼野充義
タイトルになっている「敗者の想像力」という主題が、あちこち多彩な素材に目を配りながらも、粘り強い思考とそれに見合った【勁/つよ】い文体を通して、一貫して追求されている。論じられている対象は、第二次世界大戦後の日本なので、加藤氏が一貫して―これまた粘り強く―展開してきた敗戦後論の延長だともいえるが、一昨年出版された、より体系的に戦後思想史を再考する渾身の著作ともいうべき、新書なのに六〇〇ページを超える力作『戦後入門』(ちくま新書)と比べると、こちらは主題を絞った分、鮮やかに訴えかける魅力を持った本になったという印象がある。本人の言葉を借りれば、「第二次世界大戦後の精神史と文化史の重なり合う領域への、日本と世界をつなぐ、ささやかな思想的小旅行」だ。
取り上げられる作品や著作家は、実際、非常に多様である。小津安二郎の映画、カズオ・イシグロやモディアノやゼーバルトといった作家たちによって書かれる現代の世界文学、戦後間もないころに活躍を始めた安岡章太郎のような「第三の新人」、曽野綾子、大江健三郎、目取真俊といった作家たちが、ぱっぱっと比較的スピーディに次々に登場し―というとやはり文学中心であるかのようにも見えるが―突然、ゴジラ論と「シン・ゴジラ」論が挟まり、その後、本書の第二部では山口昌男、多田道太郎、吉本隆明、鶴見俊輔などの学者や批評家が、いわばより重厚な議論の対象として取り上げられる。そしてこちらの第二部にも、宮崎駿と手塚治虫が登場する。しかし、どんな素材を取り上げようとも、常に「敗者の想像力」という主題に返っていく。その手さばきは、時々強引に見えないこともないが、舌を巻くほど見事でもある。
それでは「敗者の想像力」とは一体何か? それは敗者を思いやる、「敗者への想像力」ではない。「敗者が敗者であり続けているうちに、彼の(彼女の、とも付け加えておこう。引用者注)なかに生まれてくるだろう想像力のこと」、つまり自分自身が敗者であるという経験と自覚を通じて手に入れられる「ものの見方、感じ方、考え方、視力」のことだという。敗戦後七〇年を超えたいまでも戦後は終わっていない、というのが加藤氏の主張だが、そうだとすれば七〇年以上も「病床」にあって「戦後」はもはや「老人」のはずだが、その長い歳月の間に生み出されたものがあるはずだ、ということにもなる。
具体的には例えば、カズオ・イシグロを取り上げながら、加藤氏は、彼を欧米の現代小説家の中でも異色の存在にしているのは、彼が「敗戦国に生まれたことにつながる」敗者の想像力ではないかと言う。イシグロのSF的小説『わたしを離さないで』は、原爆の代りにクローン技術が発達した世界を描いているのだが、その舞台となる「へールシャム」という地名はヒロシマと共振しているのだ。これは言われてみてなるほどと驚かされるディテールだが、そういう細部も執拗に探索する文学探偵のようなところと、骨太の(時にやや強引な論を進める)思想家が共存している点にこそ、加藤典洋という書き手の真価があるのではないかと思う。
思想家たちに関しても、加藤氏の「敗者好み」は一貫してはっきりしている。西洋の思想を先進的なものとして受け入れ学んできた知識人の系列に丸山真男、加藤周一、桑原武夫がいるとすれば、「いま自分たちに課せられた現実を基礎に」、外国崇拝に抵抗しながら自己形成しようとした知識人の代表格が吉本、鶴見などであり、本書で加藤氏が焦点を合わせるのも後者、つまり「敗者の想像力」を鍛えた思想家たちだ。多田道太郎もまたこの系列の一人。加藤氏は多田が、サイードの『オリエンタリズム』よりも早く、「敗者の想像力」を通じて独力でポストコロニアリズムを先取りするような考え方を創出している、と言う。
そして、本書の白眉は、最後に置かれた大江健三郎の小説『水死』をめぐる厚みのある論考である。私なりに言えば、この作品は現代に先行する「昭和の精神」の総括である。大江氏は戦後民主主義の精神の強力な擁護者として知られるが、この小説では、敗戦までの民族主義的な熱狂に満ちたもう一つの「時代の精神」の検証に改めて立ち向かったのだと思う。しかし、加藤氏はこの小説にアプローチするために一つの補助線を引き、そこから一気にこの小説に秘められたメッセージを読み解こうとする。それはこの小説が書かれる前に始まった、沖縄「集団強制死」裁判という文脈である。この部分は要約してもあまり意味がなく、実際に読んでいただくしかないような気迫に満ちた書き方になっており、沖縄における「強制的自決」や曽野綾子の言う「愛」の問題が、『水死』における強姦の表象につながっているということを論証している。さらに『水死』で父が洪水の川に出ていくとき「短艇」に乗るのも偶然ではなく、これは沖縄に配備されていた特攻船舶を連想させるものだということまで、指摘している。
このように『水死』を全面的に沖縄の集団強制死に関する名誉毀損裁判に結び付けて理解するのは、加藤氏自身が認めているように、いささか「乱暴」ではある。しかし、この方法によって、これまで曖昧だったものが、急にくっきり浮かび上がってきたという印象があるのは確かである。
もっとも、小説とは当然のことながら多面的なものなので、他にも見るべき要素は色々あるだろう。私は個人的には、『水死』に現れた父の問題、「王殺し」、人間の人間に対する理不尽な暴力につきまとう「暗くて深い」感覚といった主題が、同じ二〇〇九年に出版された村上春樹の『1Q84』でもはっきりと共有されている点に興味を惹かれる。そのことを日本有数の村上春樹読みでもある加藤氏がどう考えるのか、そして村上春樹の文学はそもそも本書の主題である「敗者の想像力」という文脈から見るとどうなるのか、聞いてみたいと思った。