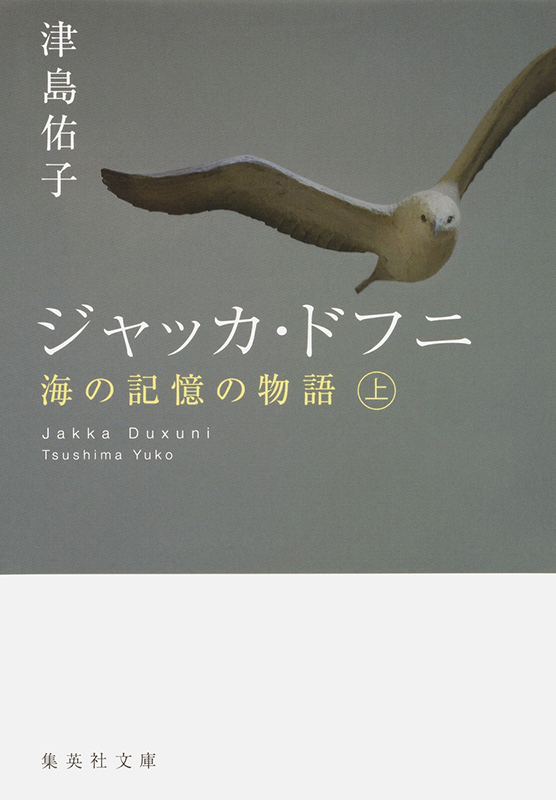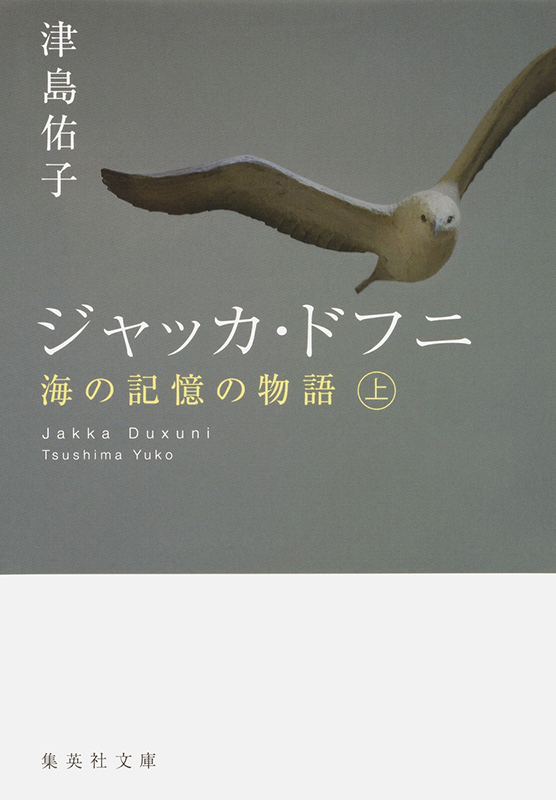【書評】歴史修正主義に抗する、先住民族の「生存の歴史」
岡和田晃
今こそ読むべきアイヌやウィルタら北方少数民族を扱った文学として、津島佑子の長編としての遺作『ジャッカ・ドフニ 海の記憶の物語』を紹介したことがある。二〇一五年夏、まだ作家が健在で同作が単行本にまとめられる前のこと、アイヌへのヘイトスピーチ問題を考える講演会での話だ。アイヌへの差別煽動は、ある意味でわかりやすい「善い朝鮮人も悪い朝鮮人もどちらも殺せ」といった形をとるのではなく、「アイヌはすでに日本人へ完全に同化している(=だから、もうアイヌはいない)」という言説を基軸とし、かつ「アイヌもそれを望んでいた(=だから、アイヌだと名乗る奴は利権が目当て)」とアイヌ自身の発言を歪曲・奪用する形で正当化していく、込み入った構成をなしている。その根底にあるのは、先住民族たるアイヌを征服して同化を強要し、言語や文化を奪ったという過去の否定だ。旗振り役を担ってきたのは、一部の政治家や漫画家などであるが、歴史修正主義に居場所を与えてしまうこの国のムラ根性に、文学もまた深い部分で加担してきた。
明治期以来、アイヌを題材とした作品は数多く書かれてきたが、その多くは「東京文学」としての「日本近代文学」の伝統からは無視されるか、よくて好奇の眼差しをもって迎えられてきた。例外的に価値が認められた作品についても、作中でのアイヌ表象自体に書き手の無自覚な差別性が込められてしまっている場合が本当に多い。一方、自らがアイヌだと告白する書き手があったとしても、その仕事のすべては「日本」に対する異物としての「アイヌ」というフィルターでもって、ひとくくりにラベリングされてしまう。同じ北方少数民族でも、さらに人口の少ないウィルタ(旧称オロッコ)となればなおさらで、だからだろうか、『ジャッカ・ドフニ』でも言及されるダーヒンニェニ・ゲンダーヌや、妹の北川アイ子が没してからは、この国で自分がウィルタ民族だと公言する者は誰もいなくなってしまった。『ジャッカ・ドフニ』というタイトルが現場で自然に口を突いて出てきたのは、アイヌでもウィルタでもない津島佑子が忘却された存在を掬い上げる雄大な構想力に、歴史修正主義に抗する想像力のあり方を感じたからだろう。
津島佑子は北方少数民族の口承文学に親しみ、そこから「とても自然につなが」る形で、キルギスのマナス叙事詩に題を採った『黄金の夢の歌』(二〇一〇)を書いた。この作品では、アイヌの口承文芸の伝統からどこまでも切り離されていることを自覚しているがゆえに、「アイヌのひとたちがたどってきた今までの現実の時間と、そして現在もつづいているさまざまなむずかしい立場を、可能なかぎり、自分の体で受けとめなければならなかった」と綴られている。『ジャッカ・ドフニ』もまた、この「体で受けとめた」ところから書かれているということは、『夢の記録』(一九八七)に収められた短編「ジャッカ・ドフニ──夏の家」を繙いてみれば一目瞭然だ。短編版では、かつて北海道を旅した際に、ゲンダーヌのいる北方少数民族資料館を在りし日の息子と訪れた幸せな記憶がよすがとなり、資料館の名称に採られたウィルタ語「ジャッカ・ドフニ」が意味する「大切なものをしまっておく場所」という言葉が、夢と現実、時間と空間の境界を超えて、作家自身の「大切なもの」を収めて活かす多様な「家」の形を招き寄せる光景が描かれていた。
もともとウィルタは、戦争を知らず階級もなく、さらには私有の概念すら持たない。この、常に移動する遊牧民ならではの自由な感覚こそが、長編版『ジャッカ・ドフニ』において──八歳で夭折してしまった息子の記憶を媒介に──銀のしずくではなく放射能が「降る降る」3・11東日本大震災以後の「現在」と、一七世紀を懸命に生きた女性チカの生涯をたどる前近代の「歴史」的な記述を融合させる導きの糸となっている。長編版の単行本とほぼ同時期に刊行された、津島佑子の短編集としての遺作『半減期を祝って』所収の「ニューヨーク、ニューヨーク」や「オートバイ、あるいは夢の手触り」では、『ピーターパン』のネバーランドのような「なにもかもが贅沢だった時代」と、そうではない現実を橋渡しする象徴として、「ニューヨーク」や「オートバイ」が語られていた。一方、表題作「半減期を祝って」は、3・11以外の何ものでもない原発事故を受けた近未来として、オリンピックの熱狂からナチスの突撃隊めいた組織が誕生、アイヌや東北人・在日朝鮮人や沖縄人らが徹底して差別される世界が予見されている。ここにはユートピアとして期待される外部が、もはや存在していない。こうした外部の喪失という感覚は、長編版『ジャッカ・ドフニ』も共有するものだ。
「あなた」という二人称を効果的に用いて語られる震災直後のオホーツク海沿岸都市・網走の光景。そこから四百年近く時間は巻き戻り、アイヌ語で「鳥」を意味する「チカップ」という名を与えられた少女の生誕、そして兄のように慕う「きりしたん」の少年ジュリアンらと一緒に虐殺を逃れ津軽〜長崎〜マカオへと移動していくエピソードが綴られ、また二〇世紀の網走が語られる。この過程から想起されるのは、先住民族の歴史を近代国民国家に対する「衰退の歴史」として捉えるのではなく、極めて過酷な入植者との接触の中での先住民族の「生存の歴史」として評価し、認識し直すという近年の北米先住民研究やアイヌ研究の動向との共振性だ(参考:坂田美奈子「歴史認識のネットワーク化へ──北海道〜北東アジア〜アラスカ先住民の生存の三〇〇年」)。アイヌに伝わる「モコロ、シンタ」の歌を自らの寄るべとしたチカップの数奇な人生は、むろん作家の想像力が生み出したものだが、彼女のように生きたアイヌがいても不思議ではないと思わせるだけの確かな手触りがある。その「生存の歴史」を想像する力こそが、歴史修正主義に陥らないためには必要なのだ。そういえば、彼女の名は、ゲンダーヌとも交流のあった刺繍家にして活動家のチカップ美恵子を彷彿させる。魂の響鳴があったのだろう。ルルル、ロロロ……と、風を介して歌が聞こえる。