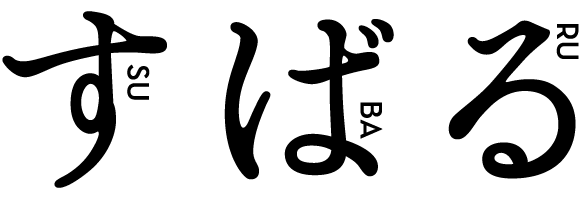【書評】私(たち)は愛されている
周司あきら
自分が自分であるだけで、否定される日常。普通ではない、生産性がない、気持ち悪い、非国民、親不孝者。だから性的マイノリティだと自覚した瞬間、とっさに自分に問うのだ。「本当に、誰からも愛されないまま生きていくのか」と。差別される側の人間として生きていかねばならない、その覚悟。簡単に持てるはずもない。世界は酷い。
そんななか日本の文学界で、李琴峰の果たした役割は計り知れない。LGBTの人々が生きる現実をこれでもかというほど書いてきた。それを読んで希死念慮と折り合いをつけた人もいるだろう。共に政治に怒った人も、LGBTのたくましい歴史に勇気づけられた人もいる。でも、まだ足りない。全然足りない。著者初となる長編紀行『シドニーの虹に誘われて』は、今後の展望をくれる。LGBTの過去も現在も踏まえて、未来へのわずかな希望を。
想像してほしい。街じゅうを虹色に染めるシドニーのマルディ・グラ(Mardi Gras)。世界最大規模のLGBTの祭典だ。「あなたは世界から祝福されている」というメッセージが溢れる。写真展も追悼記念碑もレインボーの歩道でさえも、それぞれに意味がある。奇しくも2023年2月は、日本で高級官僚の差別発言が出た時期だった。どん底の気分を晴らすように、著者はパレードを含む4泊のツアーを綴る。それは自分が一人ではないと確認する時間である。
とはいえパレードの描写はあっけない。これが実に現実的でイイ。LGBTの日常がそうであるように、注目を浴びる華やかな時間はほんの一瞬。読者はその刹那的な時間を追体験し、納得するだろう。
それにしてもシドニーは眩しい。日本の惨状に比べて、著者がそう思ったのも無理はない。最終日の空港では、仲間が「日本に帰りたくないな」と嘆いたという。その場にいなかった私でも、その嘆きは理解できてしまう。
これはもちろん、オーストラリアが先進的という単純な話ではない。オーストラリアは植民地支配でできた国だ。凄惨な過去を持つ。日本と違う点があるとすれば、迫害の歴史も忘却せず、何度でも繰り返し「先住民の土地であることの確認」をすることだ。他にも、ゲイ男性やトランス女性が殺された土地、ボンダイビーチの崖に横たわる記念碑にはこんなメッセージが。〈世界中の全ての都市の過去には深く暗い秘密がある。しかしこの類の恥ずべき事件があったことは最終的に認められなければならない。そうしてはじめて、過去に苦しんだ人たちは、自分の苦しみがようやく認識されたと感じることができる。シドニーも例外ではない〉
覆い隠して忘れ去りたい歴史を、繰り返し書き残すこと。前作『言霊の幸う国で』に負けず、本作でも著者はLGBTの置かれた状況を注視する。批判もとことんする。当事者でさえ反対デモをせざるを得なかったLGBT理解増進法は、一体誰のための法律?「ある性別を自称すればその通りになる」って本気で信じてます?
近年とくにトランスジェンダー、なかでもトランス女性差別が激しい。ただしトランスの人々は急に現れた異星人ではない。差別のレトリックも、過去の同性愛差別の使い回しなのである。性的マイノリティを差別したい連中は、LGBからT(トランス)を切り離す戦略をとるが、その手に乗ってはダメだ。彼らはLGBTをまるごと攻撃したいのだから、連帯を弱めてはいけない。
著者はシドニーのLGBTコミュニティに励まされる一方で、アンビバレントな思いも抱く。「アジアに住む私たちが欧米の歴史に共鳴し、そこから勇気とヒントを得ることがあっても、その逆はあるのだろうか。」
拭いきれない侘しさが残るなか、著者は日本独自の歴史へも目を向けさせる。同じ一冊に「歌舞伎町の夜に抱かれて」も収録するのはさすが。なるほど、歌舞伎町といえば異性愛者向けの店舗が目立つ。それでも「世界中ののけ者たちを、その欲望もろとも受け入れ」てきた歴史ある街である。欧米発祥ではない「おかま」や「ニューハーフ」といった言葉は侮蔑語として使われてきた。と同時に、当事者たちがその名乗りを引き受けてきた生の歴史と一体である。併せて、新宿二丁目のクィアな女たちを描いた『ポラリスが降り注ぐ夜』も読み返したくなった。
実を言うと、シドニーと歌舞伎町の街並みや歴史を堪能しながら、私には躊躇いが生じていた。著者はシドニーの熱狂の渦中でいくつもの「矛盾」を感じたそうだが、それとも異なる理由だ。私も、LGBTの連帯を信じている。たくさん救ってもらった。きっと仲間だ。しかし今の私は、多数派の男性であるかのように生活している。苦しい時期は去った、という感慨。このまま、まるで自分のもののようにプログレス・プライド・フラッグ(従来の6色の虹に、周縁化されてきた有色人種とトランスジェンダーを象徴する色が加わった計11色)を掲げるのは、「噓」ではないか。
そんな葛藤にまみれて、過去の自分を呼び起こした。あのとき見たかった景色。苦しくてたまらなかった時期にこそ、本書を差し出したい。今まさに本書を必要とする人がどこかにいることも、私は知っている。李琴峰は、「ここはあなたの居場所ではない」と突きつける世界に対して、「ここを私たちの居場所にしてみせる」と文学の力で戦ってきた。ほら見てよ、この景色を。まだ美しいとはいえない。でも絶対一人にさせないから。時間と場所を超えて、今この私も連なりたい。