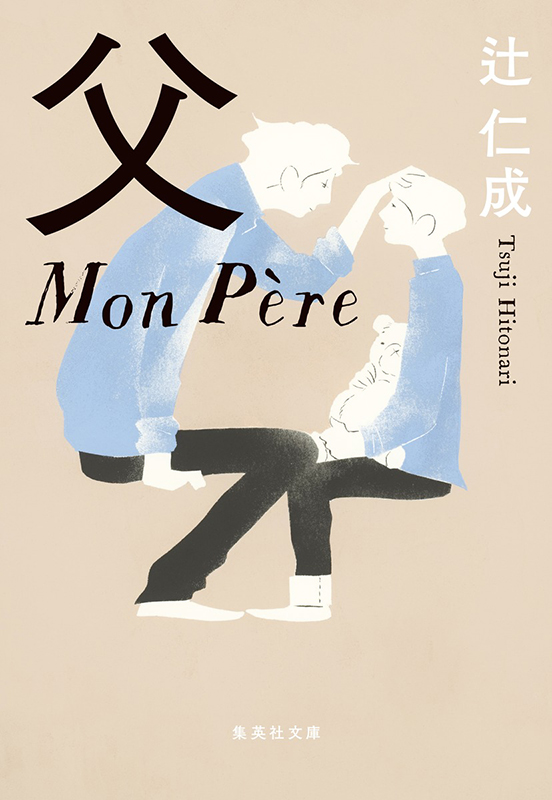【書評】記憶という動力──二〇一七年の辻仁成
倉本さおり
たとえば、十代特有のひりひりする孤独の痛みを突き刺すような筆致で綴ったデビュー作『ピアニシモ』。自分を苛めていた小学校の頃の同級生と、看守と受刑者という立場で再会した主人公の苦悩を描く『海峡の光』。亡くなった恋人の思い出に囚われ続ける男を愛してしまった女の葛藤を切り取った『人は思い出にのみ嫉妬する』。互いに忘れえぬまま別々の場所で生きることを選び取った男女の姿を追った『冷静と情熱のあいだ』、あるいは『サヨナライツカ』。
かつてそこにあったはずのもの。いまは確かに失われてしまったもの。辻仁成とは「記憶」という、不可逆的な甘やかさ、残酷さに対する狂おしいまでの執着を動力としてきた作家だ。
喪った母をめぐる、濃密な人間模様を描く『父 Mon Père』もまた、「記憶」のありようをモチーフとする物語だ。その哲学的なアプローチはこれまで以上に直接的でありながら、異文化の中で懸命に日々を重ねる人びとの姿を誠実に写し取ることで、これまでにない軽やかさと広がりを同時に獲得していることがうかがえる。辻にとっての新たな到達点を象徴する作品だといえるだろう。
*共有されない思い出
語り手の〈ぼく〉こと充路(ジユール)は、パリに住む日系二世のフランス人だ。子供の頃から家族は父と母のふたりだけ。もしものときに頼れるような親戚はいない。母・葉子が交通事故で急逝した後、成人するまでは、頑固ながら愛情深い父・泰治とふたりきりで生活を営んできた。そのぶん、父子の結びつきは一般的なそれよりも多分に強固であることを自覚している。
母の死以来、父は彼女の写真や遺品をすべてトランクにしまい込んだ。いうなれば、母の思い出を封印したわけだ。一方、そこに禁忌の匂いを嗅ぎ取った充路もまた、一度もトランクを開けることのないまま二十年以上を過ごしてきた。
しかし、生まれ育った家を出て三十歳となった現在も、充路の心には母が住み着いている。だがそれは母そのものではなく、あくまでも充路の思い出によって象られた姿なのだ。かくして父子で共有されることのなかった母の姿は、すこしずつ歪みを生み出し、ついに家族のありかたをも変えていく。
最初の契機となるのは、年老いた父が突発的に発症するようになった健忘症だ。充路のことや電話の掛け方は思い出せる。けれど直近の出来事が理解できない。自分は誰なのか? 何をしているのか? なぜそこにいるのか?──〈「充路。……すまないが、迎えに来てくれないか?」〉。携帯電話の向こうから弱々しい声が聞こえるたび、充路は父を探しにパリじゅうを駆けめぐることになる。その呼び出し音がもたらす茫漠とした不安は、充路との結婚を望む恋人・リリーとのあいだにもすこしずつ影を落とすことになってしまう。
*恋人たちの事情
そもそも、リリーとの出会いとふたりの交際が、充路と父との関係、そしてリリーとその家族との関係にひびをもたらしかねない、複雑な事情を抱えたものなのである。
事故に遭ったとき、母はリリーの父・リシャールが運転する車の助手席に座り、当時リリーの家族が所有していた別荘へと向かう道すがらにあった。つまり、彼らは恋愛関係にあったのではないか──父親の死に不審なものを感じていたリリーは、その真相を確かめるべく、五年前、たったひとりで充路のもとを訪れたのだ。当初は事実を受け入れられず、訪問を重ねるリリーから逃げ出した充路だったが、取り残された孤独を共有できる相手が彼女しかいないことに気づき、自分から連絡をとるようになる。
〈「過去は過去、それらの日々は、もう二度と戻ることのない時間の残滓なのよ」〉
真実と向き合うこと、そして父を傷つけることを恐れ、けっきょくは思い出に囚われたまま身動きができなくなっているセンチメンタルな充路とは対照的に、大陸生まれの母を持つリリーはあくまで現実的で実際的だ。まっすぐに気持ちを言葉に乗せてぶつけ、その勢いで着実に道を切り拓いていくような、チャーミングな力強さに溢れている。そんな姿に惹かれた充路は、ふたりのあいだに横たわる問題を棚上げしたまま彼女と交際を続けてきた。だが、宙ぶらりんの曖昧な状況に満足できるリリーでは当然、ない。結婚という具体的な目標を前にして、両者の齟齬は看過できない大きさに育っていく。やがて事実を知ったリリーの母・勉(ミエン・チヤン)江(ミエン・チヤン)が介入したことで、ふたりの関係そのものに暗雲が立ち込める事態と化す。
*「音」だけが現在形
日本人相手にフランス語を教えることで生計を立てている充路に対し、リリーは生物の「乾眠」と呼ばれる状態の研究をしている。water bearというグループに属する生物たちは、過酷で劣悪な環境下に置かれると、生体としての代謝を自ら止めるのだという。そして水さえ与えてやれば再び動き出して活動を始める。〈「死んでるように見えるだけで、実際は死んでない。蘇生ではなく、生き返るように見えているだけ」〉──その説明が、母という存在のありようと重ね合されることに気づいた充路は、自分なりに過去と折り合いをつけることを試みる。
〈仄かな思い出を反芻するたび、部屋に留まる懐かしい記憶の狭間に視線が潜り込む〉
充路の目に映る風景の中では、幸せだった頃の記憶が幽霊のように歩き回っている。たとえば、街でマンホールを見かけるたびに、両親と両の手をつないだ状態で引っ張り上げてもらって飛び越えたときの躍動感が蘇えるし、リリーの体から放たれる甘やかな匂いを嗅ぎ、柔らかい胸に抱かれれば、同時に母のそれを思い出す。
とりわけ強い印象を残すのは、勉江の家で大量の手料理をふるまわれる場面だ。勉江が拵えた卵スープは父の味噌汁を思い出させ、油淋鶏はから揚げを、酢豚は肉じゃが、鱸の蒸し煮は鯛の湯引きを、勉江の焼きそばは父の特製焼うどんを彷彿とさせることになる。〈嚙みしめた途端、感情があふれ出し、喉元から勝手に飛び出した。(中略)この人が子供たちを大切に育ててきた長い歳月というものが見えた〉。記憶の力によって感覚が一瞬で染め上げられる場面の美しさ、鮮やかさ、泣きたくなるほどの豊かさは、まさしく辻の真骨頂だろう。同時に、充路の五感すべてが記憶というものに紐づいていることがここでうかがえるのだ。
ところが、作中の出来事を丹念に追っていくと、じつは聴覚──すなわち「音」だけが、常に「現在」の生と結びついていることに気づく。たとえば物語の後半、バイクで二人乗りをしている時のこと。いつも変わらぬパリの街並みが思い出と共に次々と後ろへ向かって過ぎ去るなか、充路の背中越しに伝わるリリーの心音は、「いま、ここ」にある生を象徴している。通話口の向こうで、父が昔の思い出──すなわち充路が生まれたときの様子を興奮混じりにしゃべり続けるクライマックスのシーンは非常に示唆的だ。過去を紡ぐその声が漏れ出ている携帯電話を放り出し、いままさに失われようとしている命に向かって手を伸ばす充路の姿は、彼がつかみとる人生の答えを体現しているのだろう。実際、ラストシーンで充路なりの「乾眠」状態を意外な形で破るのもまた、新しく買い換えた携帯の呼び出し音なのだ。
*「いま」を更新していくもの
五月二十日に公開が予定されている辻仁成の監督最新作『TOKYOデシベル』は、九五年に発表された「音の地図」を大幅に改作し映像化した作品だ。東京じゅうの音を集めて解析することで、「東京の音の地図を作る」という夢を持つ大学教授の宙也と、彼の恋人であったフミ、宙也とフミに再びかかわりを持たせようとする女マリコ。過去の喪失を埋められずに生きてきた男女三人が織りなす、不器用な愛の物語を描く。
かつて妻に去られた男が、残された子供を養いながら、ままならない愛の姿を模索する。シンプルに構造だけを抜き出して比べてみても、本作と通底していることがうかがえるが、刮目すべきは「音」というモチーフのありようだ。作中の後半、ひとまず完成した「音の地図」を宙也に見せられた人びとは驚嘆し、〈「東京が生きているみたいだ」〉という感想を漏らす。「音」で構築された地図が、現在進行形の「生」を象る──それは本作の主題とぴったりと重なる。
他にも象徴的な場面がある。絶対音感を持ち、ピアノの調律を生業にしているフミは、ピアノを「常に手をかけてやらなければいけない生き物」だと定義した上で、宙也にこう告げる。〈「私たち、ずっと音がずれてたわ」〉。その台詞にこれまでの解釈を照らし合わせるなら、「音」──すなわち「いま、ここ」が二人のあいだでチューニングされてこなかったことを意味するのではないだろうか。
〈「愛がなくなった、と判断をしたからこそ、君のママは私の父に走ったのでしょ? 愛は繋ぎとめるものじゃなくて、常に更新し続けないとならないものだと私は思う」〉
『父 Mon Père』の終盤、リリーが充路に告げる言葉は、この物語のテーマを代弁していると同時に、辻仁成という作家がこれまでに通り過ぎてきたすべての時間や物事の、幸福な結晶なのだろう。そこにある澄んだ響きは、次作の発表を心待ちにさせる。