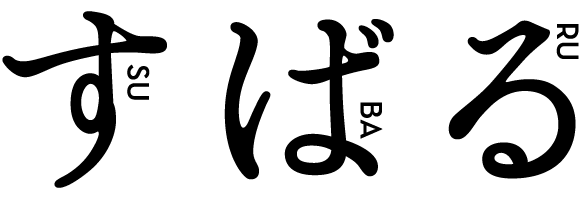第49回すばる文学賞を受賞したのは、選考会で評価がまっぷたつに分かれた異形の青春小説「粉瘤息子都落ち択」。著者・更地郊さんのこれまでの歩みをたどります。
*
――「受賞のことば」にもありましたが、言葉で何かを表現するようになった原体験は、ネットでのやり取りにあるそうですね。
更地 受験に失敗して、周囲になじめない生活を送っていたときに東日本大震災が起きたんです。いろいろ不自由を強いられるなかで親のお下がりでiPod touchを貰って、真っ暗な部屋でずっとネットを見ていたのを憶えています。ツイッターで流れてくる面白い投稿なんかを追いながら、未知の語彙や言語感覚に感心してました。そういう投稿ができる人たちの興味を惹きたくて、やがて自分でも奇を衒った投稿をするようになっていったという経緯です。
――そこで自身の言葉が誰かの元に届く手応えを得たということでしょうか。
更地 いえ、それが全然センスがなくて、ひたすらつぶやいては無視されるっていうのを3、4年続けていました。大学に入って気づいたのが、好みの言語感覚の人たちは読書家だという傾向で。自分は読書遍歴が薄いことが本当にコンプレックスなんですが、幼少期から培ってきた読書量や知識量の差は永遠に埋まらないんだろうなと。それに対する焦りもあって、彼らが読んでいたSF作品を手にとってみたら一気にハマってしまって。
――具体的にはどの作品だったんですか。
更地 伊藤計劃さんの『虐殺器官』、月村了衛さんの『機龍警察』、小川哲さんの『ゲームの王国』あたりのメジャーどころですね。以降、SF以外も読むようになるんですが、一番衝撃だったのは佐藤亜紀さんの『天使』。それまではフィクションの表現手段としては映像が王様だと思っていて。でも、小説でしかなし得ない表現、感動が存在するんだというのをまざまざと見せつけられました。いわゆる超能力を持った人間たちが登場する物語ですが、彼らの人知を超えた感覚、第六感が、読者にいともたやすく伝わるように描写されていて。
――そこで受けた衝撃がご自身の創作へと繫がっていくわけでしょうか。
更地 そうですね。とはいえ、書き始めたのは大学卒業してからです。新卒で最初に就職したのがゲーム会社で、シナリオ関連の部署に所属したかったので、ポートフォリオ代わりに当時プレイしていた「アイマス」の二次創作を3、4本書いたりしました。でも、思いのほか手応えもなく。そんな体たらくでしたが、物語を作るなら一次創作も書けるべきだと思って、オリジナルを書くようになったという流れです。
――そして実力を測る目的で文藝賞に応募したら、最終候補に残ったんですよね。
更地 当然落選でしたが、選評で「街のノイズが描かれていない」と指摘してくださった選考委員がいて。じゃあ、いっそ街のノイズに着目したものを書いてみようと思ったのが「粉瘤息子都落ち択」です。もともと散歩をしながら公衆便所や自販機の落書きをスマホで撮って集めていたんですが、街中の匿名でインディな叫びには異様なエネルギーと面白さを感じていて。そこに粉瘤とかテプラとかマウンテンデューとか、あまり小説のモチーフにはならなそうな、なるべくくだらないものを盛り込みながら話を組み立てました。
――主人公・野中の徹底したうだつの上がらなさは、癖になるおかしみがあります。
更地 情けない男を主人公にした物語なら書けるかもしれないと思ったんです。自分自身、野中みたいな汚い部屋に住んで、粉瘤をつぶして、スト6の試合動画を観ているだけの生活をしていたので。とはいえ、書きながら人間の心情というものをちゃんと描けているのだろうかという不安がずっと消えなくて、それは今でも確証はないままです。
――野中と友人の忍は、ホモソやBLに回収されない独特な友情で結ばれていますよね。不器用に関わりながら、ゆるやかに回復曲線を描いていく様子が印象的でした。
更地 二次創作をするなかで、そのキャラ同士で起こり得る距離感の揺れ動きを意識してました。今回ふたりの男が話の軸になり、じゃあまだ見ぬ距離感、新しい関係性のバリエーションを描けないだろうかと思って。結果、成人男性が高校生をゴリゴリ説教しながら追い詰める場面が最大の山場という、どこまでも情けない物語になりましたが(笑)。
――ラストの野中の「都落ち」も、とても切ない余韻が残ります。
更地 深夜のファミレスに缶詰で終盤の展開を書いているとき、耳の裏が痒くなってポリポリやってるうちに、野中と同じく自分も粉瘤がつぶれたんです(笑)。小説家は自分の作品に現実が追いつく瞬間を経験することがあるそうですが、「これのことか!」って、指と耳が血まみれの状態でひとりニヤニヤしてました。でも、そういう物語のスケールに見合った小ささ、情けなさが自分らしいのかなという自覚はあるので、いい意味でくだらなさを大事にしながらこれからも書いていきたいです。
すばる2025年11月号より
聞き手・構成/編集部 撮影/下城英悟